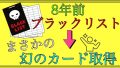「なんとなく使いづらい」オフィス、原因は“ゾーニング”かも?
「会議中に電話の音が気になる」「来客対応と作業スペースが近くて落ち着かない」
そんな声が、オフィス内で聞こえてきたことはありませんか?
実はこれ、“ゾーニング”がうまくできていないことが原因かもしれません。
ゾーニングとは、オフィス内を目的や機能ごとにエリア分けする設計手法のこと。広いオフィスに限らず、小規模なオフィスでも取り入れることで、働きやすさ・集中力・来客対応の質などが大きく変わってきます。
この記事では、オフィスの移転やリニューアルを検討中の企業担当者様に向けて、小規模オフィスでもすぐ実践できるゾーニングの考え方と活用法をわかりやすくご紹介します。
ゾーニングとは?基本の考え方を解説
ゾーニング=“空間の役割をはっきりさせること”
ゾーニングとは、オフィス内の空間を「何をする場所なのか」を明確に区切る考え方です。
たとえば次のような用途でエリアを分けます。
- 集中して作業するワークスペース
- 来客応対や打ち合わせに使うミーティングスペース
- ちょっとした会話や休憩ができるリフレッシュスペース
- 電話やWeb会議に使えるパーソナルブース
こうした機能ごとの区分けが明確でないと、作業の質が下がったり、ストレスが溜まったりする原因になります。
小規模オフィスでも活用できるゾーニングの具体例
スペースに限りがある小規模オフィスでも、アイデア次第で機能的にゾーニングできます。以下の工夫がポイントです。
パーティションや家具を活用する
- 低めの棚や観葉植物でゆるやかに仕切ることで、閉塞感を避けつつ空間を分けられます。
- 吸音パネル付きのデスクや移動式パーティションを活用すると、音の分離も可能です。
フロアマットや照明でエリア感を演出
- カーペットの色を変えることで、明確な“エリアの境目”を視覚的に作れます。
- 照明の色温度を変える(作業スペースは白色光、リラックススペースは暖色系)ことで、心理的なゾーニングも可能です。
スペースの“時間割”を活用する
スペースが足りない場合は、時間帯によって用途を変える工夫も有効です。
- 午前中:集中業務スペース
- 午後:打ち合わせスペース
- 夕方:オンラインミーティング用に
予約制やスケジューラーを活用することで、共有空間を有効活用できます。
ゾーニングのメリットとは?
ゾーニングにはさまざまなメリットがあります。小規模オフィスこそ、空間の使い方次第で効率が大きく変わるため重要です。
1. 生産性の向上
- 業務に集中できる空間と、雑談や休憩できる空間を分けることで、メリハリのある働き方が可能に。
- 雑音や周囲の動きに邪魔されにくくなるため、パフォーマンスが安定します。
2. コミュニケーションの活性化
- 休憩スペースや共有スペースが明確に設けられていれば、自然なコミュニケーションのきっかけになります。
- 会話の場所と業務エリアを分けることで、無用な気遣いが減り、関係性も良好に。
3. 来客対応の印象アップ
- 受付や打ち合わせスペースを分かりやすく配置すれば、訪問者にとっての安心感・清潔感がアップします。
- 社外の人に業務スペースを見せずに済むレイアウトは、セキュリティ面でも安心です。
小規模オフィスでゾーニングを成功させる3つのポイント
1. オフィスの“動き”を観察する
まずは現在のオフィスの使い方を観察し、「どこで誰が、何をしているか」を洗い出します。
意外と**“動線がかぶっている” “物音がストレスになっている”**などの課題が見えてきます。
2. エリアの“優先順位”をつける
限られた面積では、すべてを完璧に分けることは難しいため、最優先すべきエリア(例:会議室・静音ブースなど)を明確に決めることが重要です。
3. 将来の変化も見越しておく
レイアウト変更に柔軟に対応できるよう、可動式家具や、配線の自由度が高いレイアウトを意識しておくと安心です。
ゾーニングの工夫で「狭さ」を強みに変える
小規模オフィスには「スペースが足りない」という課題がつきものですが、ゾーニングの工夫次第で“狭くても機能的な空間”に生まれ変わることができます。
大切なのは、使う人の働き方に寄り添い、目的ごとに空間の“役割”をデザインすること。
その発想があれば、限られたスペースの中でも驚くほど快適で効率的なオフィス環境が実現可能です。
まとめ|ゾーニングで働き方をアップデート
- ゾーニングとは「空間に役割を持たせる」考え方
- 小規模オフィスでも、家具や光・時間割などの工夫で実践できる
- 生産性・コミュニケーション・印象アップなど多くのメリットがある
- 成功には観察・優先順位・柔軟性の3点がカギ
オフィスの移転やリニューアルを機に、「ゾーニング」を意識した空間設計に取り組んでみてはいかがでしょうか?
小さな工夫が、社員の働き方と満足度を大きく変える第一歩になるかもしれません。